
北京
PM2.577

3/-2

北京
PM2.577

3/-2
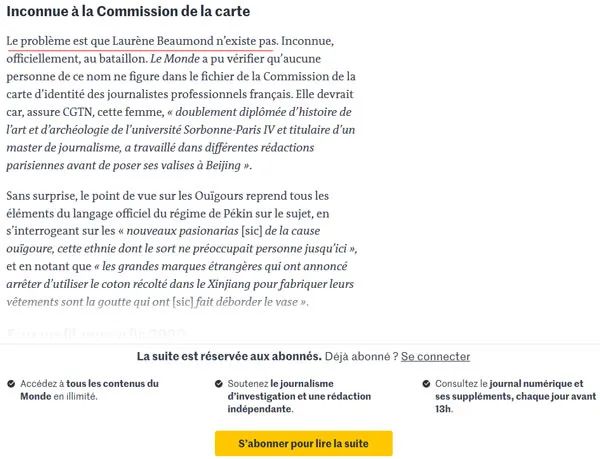
仏誌『ル・モンド』はこのほど、「CGTN(中国グローバルテレビジョンネットワーク)のフランス語チャンネルは『ローレン・ボーモンド(Laurène Beaumond)』という架空のフランス人フリージャーナリストの記事を掲載して中国政府の新疆政策を肯定している」と報道しました。その根拠は、フランス記者協会に「ローレン・ボーモンド」という名前の記者が登録されていないからだとしています。
しかし、別のフランスメディアは調査を経て、「ローレン・ボーモンド氏は実際に存在している人物で、しかもフランスの大学でニュースを専攻したエリートである」と結論しました。これを受けて、仏誌『ル・フィガロ』はボーモンド氏本人にインタビューも行っています。
では、なぜフランス人記者協会のリストにボーモンド氏の名前が無かったのでしょうか。その答えは、「ローレン・ボーモンド」が彼女のペンネームだったからです。フランスでは真実を語る記者は様々な政治的リスクにさらされるため、彼女はやむを得ずペンネームを用いて新疆の記事を発表したのです。
ボーモンド氏の憂慮は決して大袈裟なものではありません。たとえば、フランス・ストラスブール大学法学院のクリスチャン・メストレ(Christian Mestre)元学長は2019年、中国の新疆政策に賛同する言論を発表したことで、様々な圧力をかけられて辞任に追い込まれてしまいました。
また、フランス人作家で記者でもあるマクシム・ビバス(Maxime Vivas)氏は新疆を2度訪れ、書籍『ウイグル族についてのフェイクニュースの終焉』を出版しましたが、フランスの主流メディアから攻撃され、いかなる反論のチャンスも与えられないどころか、「これから二度と著作を出版するチャンスはないだろう」とまで恐喝されました。
こうした過去の事実から、ローレン・ボーモンド氏がペンネームを使用した理由は納得できるでしょう。ボーモンド氏は中国で7年間暮らし、2014年にウルムチに住む夫と結婚して新疆で暮らしました。『ル・フィガロ』のインタビューでボーモンド氏は、自身が書いた記事について、「3月24日にCGTNと連絡して寄稿したもの。数日後にCGTN側からの確認を受けて掲載された。文責などすべての責任を取る覚悟はある」と表明しました。同氏はまた、「新疆ではいかなるジェノサイドも行われていない」と断言しました。
そんなボーモンド氏に送られるのは、疑いの眼差しなどではなく「Bravo!(よくやった!)」という声援であるべきです。彼女こそ、真実を語る勇気ある記者です。
ところで、最初に疑念の目を向けた当の『ル・モンド』がこの真実にどう対応したかというと、なんと当該記事を「有料」にし、閲覧を制限してしまいました。中国を中傷し、ボーモンド氏を貶める報道をしておいて、何も無かったかのような振る舞いをすることが許されるのでしょうか。
『ル・モンド』よ、謝罪をするべきです。(Lin、謙)