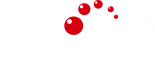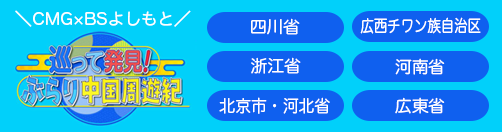北京
PM2.577
23/19
【観察眼】作家・伊藤比呂美さんが実感した中国のリアルに思う
作家・伊藤比呂美さんが8日間の中国訪問を終え、帰国した。中国では、女性の身体の変化や、老いていくプロセスをありのままに綴った彼女のエッセイ集が、若い女性の間で共感を呼んでいる。滞在中、伊藤さんは上海、杭州、北京、天津を訪問。読者の人生相談に応じ、各地の大学で日本文学史の講演会を開き、中国の学者や学生と交流を深めた。
北京滞在中、伊藤さんは当放送局のインタビューで、今回の旅は「めちゃめちゃ面白かった」と話し、日本のメディアはネガティブな中国報道が多く見られるが、中国のリアルは「ぜんぜん違いました」と述べた。伊藤さんの過去の訪中は30数年前に、トランジットのため北京で一泊しただけとのことで、実質的には今回が初めて中国滞在だった。

7歳で書道を始め、高校では「漢詩」に出会い、大学でも「漢詩」を履修した伊藤さんは、中国文化に馴染みがあった。しかし、これまでに国際結婚をきっかけに生活の拠点を米国に移し、日本に住む親の介護などに追われ、いままで中国旅行をする機会が得られなかったという。さらに、日本文化にしても中国文化にしても、「自分が興味をもつのは全部古代のもので、今の中国で何が起こっているかには興味がなかった」と語り、「不思議でしょ」と笑った。
今回の訪中で彼女には驚きの「発見」があった。
「中国の大学で講演する時に、黒板に漢字を書くと、みなさん分かるんですよ。それはアメリカやドイツではありえなかった。やっぱり漢字を使える我々と漢字が使えない人たちとでは、相互理解が全然違う」
「浅く広くという形のコミュニケーションは、日中の方がずっと取れる」――これこそ、伊藤さんが今回の訪中で心打たれた瞬間だった。
欧米とアジアでは、作品の受容の仕方にも違いがあるという。中国・韓国で翻訳されている彼女の作品は、女性の生活にフォーカスしたエッセイ集だ。それに対し、欧米では小説や詩をはじめ、思想性を重んじる作品が“文学”として多く読まれている。その背景の一つに、アジアの国々では「基本的な家族制度や生き方の倫理などが似ている」ことがあると伊藤さんは見ている。アジアの近隣同士だからこそ通底する何かがある。伊藤さんは今回の訪中でそう痛感したという。
きめ細かな観察眼を持つ伊藤さんは、中国の女性のイメージについて、次のように語った。
「実は1980年代に受けた印象では、中国の女は男と同格に仕事ができる。(日本と違い)なんでもできて、羨ましいなと思っていました。でも今回来てみたら、日本とあまり変わらないかもしれないと思いました」
40年前に伊藤さんが中国人女性に抱いていた印象は、遠目から見た理想化された像であり、今回の旅ではより近距離から、ありのままの姿を捉えたようにも思える。また、彼女が気付いた中国人女性の変化とは、改革開放が進むにつれ、女性たちの価値観や追い求めるものの多元化を物語るものでもある。
一方、「古代の文化には興味があるものの、今のリアルな中国にはあまり関心がない」という言葉には考えさせられた。中国側としては、現在の社会の魅力をもっと分かりやすくPRする必要があるのではないか。そんなことが課題として浮き彫りになる指摘であった。
中国の歴史・伝統文化と現在を切り離して捉えるという見方が生じたのはなぜだろうか。伊藤さん個人の好みや性格もあろう。しかし、ややもすれば、色眼鏡をかけた、ネガティブな報道がされがちな環境で暮らしていれば、人は自ずと中国と距離を保ちたくなるようなことがあるのではなかろうか、そう深読みしたくなる。

伊藤さんの北京滞在中、中国の出版社は彼女が10年以上続けているという「ズンバ」のイベントを開催した。68歳になる伊藤さんは1時間にわたり、中国の約100人の読者とともに、ノリノリの音楽に合わせて汗を流した。「日本の作家はたくさんいるが、中国で読者のみなさんと一緒にズンバを1時間も踊った人は私だけだ」、と伊藤さんは誇らしそうに語った。
「10年早く来たかった。そしたら、もっと関われて、何度も来ることができたなと思っています」
中国との別れを惜しむ言葉のようにも聞こえた。
伊藤比呂美さんが実感した中国のリアルとは何だろうか。複雑なものは何もなかった。ズンバでともに流した汗、熱気、笑い、拍手が裏付ける人々のピュアな思い、フレンドリーさ、元気さ。日本人と変わらぬ喜怒哀楽があり、その感情をともに分かち合うことができる。伊藤さんはそう確信した。
中日は永遠の隣人であり、同じ漢字文化圏にある。色眼鏡を捨て去り、相手に近づき、リアルに迫ってこそ見えてくるものがある。これこそ、伊藤比呂美さんの中国紀行がもたらしてくれた気づきではなかろうか。(CGTN日本語部論説員)
KANKAN特集